COLUMN
札幌で働きたい学生に
オススメの記事
- キャリア形成
事前準備で差がつく!キャリア教育×オープンカンパニー活用マニュアル
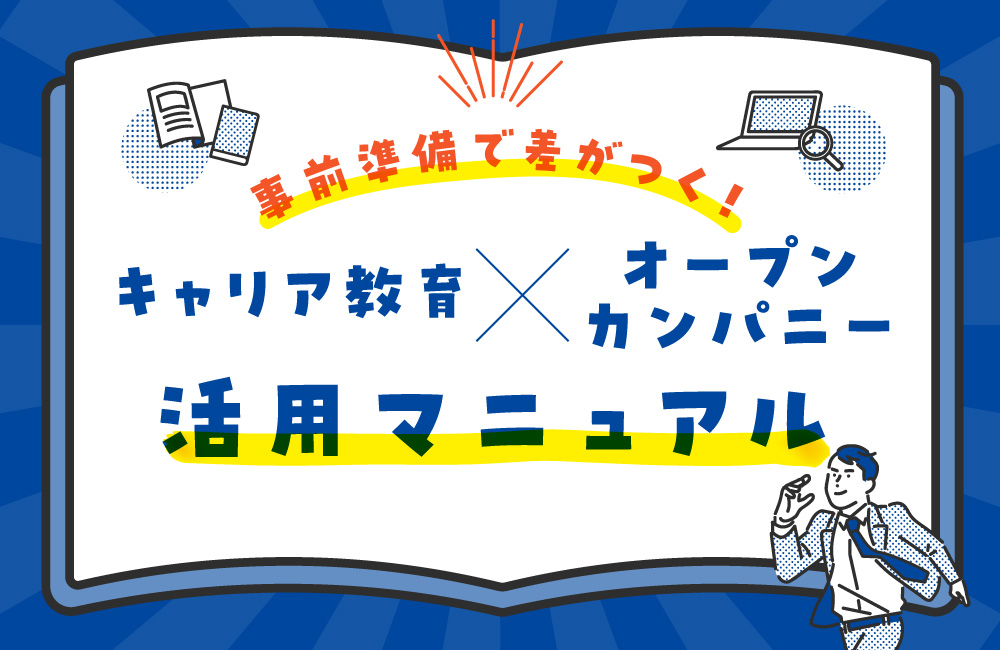
キャリア教育とは
近年、大学や専門学校では「キャリア教育」がますます重要なテーマになっています。
キャリア教育とは、社会の中で生きる力や働く力を育てる教育のことです。
学生はキャリア教育を通して、「自分はどんな仕事に向いているか」「どんな形で社会に関わりたいか」を考えるきっかけを得ていきます。
現代は社会の変化が速く、働き方も多様化する時代。いま求められているのは、「どんな会社に入るか」よりも、「どのように社会に貢献できるか」という視点です。
そのため、大学では「知識を学ぶ」だけでなく、「学んだことを社会でどう生かすか」を考える教育が求められています。
キャリア教育は、学生が在学中から社会とつながり、自分なりのキャリア観を育てていく大切な仕組みとして注目を集めています。
その中で、企業と直接関わる体験型プログラムである「オープンカンパニー」は、キャリア教育の実践手段のひとつです。
オープンカンパニーを通じて企業を訪問し、社員の話を聞いたり、現場を見学したりする中で、学生は「働くことのリアル」を感じとることができます。
札幌でも多くの大学がこの仕組みを取り入れ、地域企業と協力しながらキャリア教育の充実を図っています。
事前に目的を整理し、オープンカンパニーでの体験を経て、終了後学びを振り返るという流れをつくることで、知識だけでなく実感を伴った学びへとつながります。
このコラムでは、授業との連携方法や学生の準備の進め方、先生や企業がどのように関わるとより効果的かなど、キャリア教育を深めるためのポイントを紹介していきます。
授業連携パターン
キャリア教育の中でオープンカンパニーを取り入れる方法は、学校のカリキュラムや企業の受け入れ体制によってさまざまです。ここでは、よく使われている3つのパターンを紹介します。
1. 授業内連携型
授業の一環としてオープンカンパニーを取り入れる方法です。たとえば「キャリア形成論」や「地域産業論」などの科目で、地元企業を訪問したり、社員から話を聞いたりします。
実施例
- 授業内で事前学習を行い、企業訪問の目的を整理する
- 訪問後にレポートや発表を通して学びを共有する
- 先生と企業担当者が事前にテーマを設定する(例:「地域課題と企業の役割」など)
この形式の良いところは、授業の学びと現場体験をセットで考えられることです。成績評価や授業目標に結びつけることで、学生がより意欲的に取り組めます。
2. 授業外連携型(課外講座・短期集中型)
夏休みや春休みなどの長期休暇に合わせて、キャリアセンターが主催する形で実施するタイプです。キャリアセンターが主催する「企業見学プログラム」では、1社をじっくり訪問するものから、複数企業を連続して回るツアー形式まで、さまざまな形があります。
特徴
- 授業の枠にとらわれず、学生が興味のある業界を自由に選べる
- 先生・キャリアセンター・企業の三者が柔軟に連携できる
- 学生同士が学年や専攻を超えて交流しやすい
とくに札幌ではIT・観光・食・建設・医療など産業の幅が広いため、学生が複数業界を横断して体験できるのも魅力です。授業外でも、先生やキャリアセンターがサポートに入ることで、教育効果を高めることができます。
3. 共同探究・PBL型(課題解決連携)
近年増えているのが、「Project-Based Learning(課題解決型学習)」の形式です。企業が実際に抱える課題(例:人材採用・地域活性・商品企画など)をテーマに、学生チームが調査や提案を行うスタイルです。
進め方の例
- 企業が学生にテーマを提示(例:「若者に向けた地域PRの方法」など)
- チームで調査・インタビューを行い、企業担当者に中間報告
- 授業の最終回に成果発表会を実施
学生にとっては授業で学んだことを社会で試す機会となり、企業にとっても若い視点から新しいアイデアを得られるメリットがあります。学校と企業が“学びの共同開発者”として関わることで、キャリア教育の実践性がさらに高まります。
キャリア教育とオープンカンパニーの関係に、これが正解という形はありません。授業の中で取り入れる方法もあれば、課外活動や企業との共同プロジェクトとして進めることもあります。
どんな形であっても「学ぶこと」と「体験すること」をつなぐ意識を持つだけで、オープンカンパニーは見学の場から、将来を考える大切な学びの時間へと変わっていきます。
学生の準備チェックリスト
オープンカンパニーは「体験の場」であると同時に、「社会人としての第一歩」でもあります。参加する学生が事前にしっかり準備しておくことで、吸収できることがぐっと増えます。
以下のチェックリストは、札幌市内の大学で実施されているオープンカンパニーの学習内容を参考にまとめたものです。
【事前準備チェックリスト】
基本準備
□ 参加企業のホームページを確認した
□ 事業内容・業界情報を簡単にメモしておいた
□ 服装・集合場所・持ち物などの案内を確認した
自分の目的を整理
□「なぜこの企業を選んだのか」を一言で説明できる
□ 自分が興味を持っている仕事の分野を把握している
□ 体験を通して学びたいことを3つ挙げられる
当日のマナー・心構え
□ あいさつ・自己紹介を練習した
□ グループワークや社員交流で積極的に発言する意識を持っている
□ SNSなどへの投稿ルール(写真撮影・守秘義務)を理解している
振り返り準備
□ 終了後すぐに印象に残ったことを記録する
□ 授業やレポートにどう活かすかを考える
□ 同期や後輩への情報共有を意識する
ダウンロード版では、オープンカンパニー参加に役立つチェック項目をさらに詳しくまとめています。
先生・企業向け Q&A
キャリア教育とオープンカンパニーの連携に関して、先生や企業の方からよく寄せられる質問をまとめました。
Q1. 企業側として、どんな準備が必要ですか?
学生が安心して参加できるよう、当日の流れを明確にしておくことが大切です。受付・説明・見学・交流などのタイムスケジュールを事前に共有し、担当社員の役割を決めておくとスムーズです。
また、「どんな姿勢で参加してほしいか(例:質問歓迎・観察中心など)」を伝えておくと、学生の積極性を引き出しやすくなります。
Q2. 授業の一環として実施する場合、教員はどこまで関わるべき?
先生は「学びの橋渡し役」として、事前・事後のフォローに重点を置くのが効果的です。
訪問前に目的を整理するワークシートを実施し、終了後には振り返りレポートをまとめるよう促します。授業内で発表会を開けば、学生同士の学び合いにもつながります。
Q3. 学生が消極的な場合、どう支援すればいい?
「企業に行く=就活の第一歩」という意識を持たせることが効果的です。
単なる見学ではなく、「社会人の働き方を学ぶ時間」として伝えると意識が変わります。また、グループ単位での振り返りや発表を取り入れると、互いの気づきを共有できる良い機会になります。
Q4. 企業にとってのメリットは?
若い世代と交流することで、自社の魅力を客観的に見直すきっかけになります。学生からの質問を通して、自社がどのように見られているかを知ることもできます。
さらに、地域との関係づくりや将来の採用活動にもつながるなど、長期的な効果も期待できるでしょう。
まとめ
オープンカンパニーは、学生にとっては「社会を知る第一歩」、先生にとっては「学びを社会とつなぐ教育ツール」、そして企業にとっては「未来の人材と出会うチャンス」です。
この3者が目的を共有し、しっかりと事前準備を行うことで、キャリア教育の質はさらに高まります。
授業と企業での体験をつなげることで、学生は“就活の練習”にとどまらず、自分の将来や生き方を考えるきっかけを得られます。
札幌という地域の中で、学校と企業が手を取り合いながら学生の成長を支えていく。
その輪が広がっていくことで、次世代のキャリア教育はもっと豊かに、そして実践的に育っていくでしょう。
